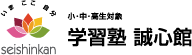こんにちは、講師の伊東です。今日は“塾講師”についてお話ししたいと思います。
私は大学に入ってから講師のアルバイトを始め、家庭教師と塾講師を経験しました。他のアルバイトもたくさんある中で講師を選んだ理由は、単純に私がメニュー等を覚えられそうにないというのもありますが(笑)、なんといってもやりがいを感じるからです。
人に教えるのは難しく、生徒によって成績や理解力はバラバラなので一通りの教え方では理解してもらえないことも多いですが、どう言ったら伝わるかなと模索し、ちゃんと伝わって正解してくれた時はとても嬉しく感じます。また、理解してもらえるように工夫することが、私自身のスキルアップに繋がっていると思います。
生徒との信頼関係の構築や、授業の雰囲気作りも講師の重要な役割で、これがしっかり出来ていないと円滑な授業はできないと思っています。生徒とたくさんコミュニケーションをとったり、出来るだけ面白い表現を使ったりして生徒が受け身ではなく能動的になってくれる授業を目指しています。
私が受験生で塾に通っていた時に、いつも的確に教えてくれて一緒に考えてくれる大好きな講師がいました。勉強するためなのはもちろんですが、その人に教えてもらいたくて塾に行っていた節もあります(笑)誠心館の生徒たちにも、先生に教えて欲しいから来た!と言ってもらえるようにたくさん話をして信頼してもらい、伝わる指導をするのが私の今の目標です。