 こんばんは、上熊須です。
こんばんは、上熊須です。
入試が終わり、合格の連絡が来て喜んでる方も多いでしょう。ですが、実は期末試験がもうすぐそこまで迫っています。入試が終わったのになんで勉強しないといけないんだと思うかもしれませんが、この学年末のテストで勉強を怠ると大変なことになります。
入試のあとは普段よりも勉強をしなくなります。このまま勉強せずにテストを受けると、間違いなく今までで一番悪い結果になるでしょう。そしてこのテストの結果は、進学する高校にも送られます。成績の落ち方が激しいと先生に目をつけられるかもしれません。さらに高校1年生の授業は中学3年までに学んだことを全て使います。3年の学年末が悪ければ、当然高校のテストにも響きます。
高校の勉強や、その後の大学入試を楽にするためにも、この学期末は頑張って勉強しましょう。
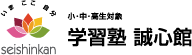
 講師の宮本です。今冬一番の寒さが来ましたね。休みの日なら外に出たくないのでそんな時は家で本を読むに限ります。
講師の宮本です。今冬一番の寒さが来ましたね。休みの日なら外に出たくないのでそんな時は家で本を読むに限ります。 こんばんは、講師の伊東です!昨日は私立高校の入試でしたね。中3受験生の皆さんお疲れ様でした!高3の皆さんも二次試験まっただ中ですが、最後まで気を抜かず、1つ1つの試験で全力を出し切れるように頑張ってください(^^)/
こんばんは、講師の伊東です!昨日は私立高校の入試でしたね。中3受験生の皆さんお疲れ様でした!高3の皆さんも二次試験まっただ中ですが、最後まで気を抜かず、1つ1つの試験で全力を出し切れるように頑張ってください(^^)/
 こんばんは!講師の丸野です。最近読書にはまっていてとくに山田悠介という方の本にはまっています。おすすめは「その時までサヨナラ」という本です。とても感動する内容なので皆さん是非一度は読んでみてください!
こんばんは!講師の丸野です。最近読書にはまっていてとくに山田悠介という方の本にはまっています。おすすめは「その時までサヨナラ」という本です。とても感動する内容なので皆さん是非一度は読んでみてください!