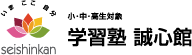12月に入り体験学習が続いております^^
昨日は天王寺川中2年生と安倉小6年生、本日は安倉中2年生と荒牧中2年生の生徒が体験学習に来てくれました!体験授業の講師は昨日が宮本先生で本日は上熊須先生と丸野先生が担当。
誠心館の講師は教え方が上手いのでかなり理解してもらえたと思います。
また、ここ最近は紹介での体験が増えてきているのが嬉しいですね。
誠心館で勉強の仕方や考え方を理解して、何でも自分でできる人間に育ってほしいと思います。
写真は須貝先生が伊丹北高1年生と三田学園高1年生を個別指導しているところ。チャート式を徹底解説。笑い(?)を取りながらの指導はさすがです!
奥では丸野先生が伊丹西高1年生、東中1年生、荒牧中2年生を個別に指導中。