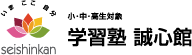こんにちは、中村(宏)です。
先週は中学校の期末試験が終わり、生徒は夏休みが待ち遠しいようです。
今回のテストでは、成績が伸びた子や現状維持だった子や少しだけ前回より下がった子と結果は様々でした。大幅に点数が下がった子はいなかったので、みんなよく頑張ってくれたと思います。
今日のブログでは、成績の伸び悩みについて書きたいと思います。
成績の伸び悩みですが、これは成績を上げるうえで誰もが経験することなのです。成績の伸び悩みの原因として、①基礎力不足と②勉強法の非効率が挙げられます。①基礎力は普段の間違えなおしを丁寧にしていれば、いつの間にか身に着きます。
重要なことは勉強法を改善することです。これに関しては、人によってすぐできる人と時間がかかる人と差が出ます。勉強法の改善で大事なことは生徒自身がその改善によるメリットに気づくことです。生徒としては「勉強を頑張っている」という自信を持っているので、勉強法が非効率だということをすぐには認めることができません。そのため、「気づき」は少しずつしか成長しません。保護者の方であれば、成績の伸び悩みに不安を持たれると思いますが、この時期は優しく見守ってあげてください。
基礎力を身に着けて、勉強法を改善した生徒は確実に成績が上がります。この境地に至れば、成績は勝手に上がり90点台の点数も難なくとることが出来ます。勉強法の改善ができた生徒は、自分で勉強法を開発できるようになります。中学生でここまでできたら高校生の勉強でも怖いものなしです。
私の中学生の頃の恩師が、「中学生の成長の証は、中学校を卒業したあとに国語や数学などの知識をすべて削除して、そのあとに残るものである。」といっていました。自分で考えて物事に取り組めるという力をつけることこそが成長なのです。
これからも生徒の真の成長にしっかり向き合っていきたいと思います。