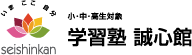こんにちは、中村(宏)です。
「勉強をしよう」と思っても、行動できないという経験が誰にでもあると思います。今日はこの原因について書きたいと思います。
ところで、「勉強する」という言葉を聞いてどのような行動を思い浮かべますか。ある人は単語を覚えること、またある人は計算をすることを思い浮かべていると思います。単に「勉強する」といっても、「具体的に何をする」かは人それぞれです。すぐに行動するためにはこの「具体的な行動」を思い浮かべる必要があります。例えば、料理を作ってくださいという指示よりも鍋を作ってくださいという指示の方がすぐに行動に移ることができます。さらに、鍋を作ってくださいという指示よりももつ鍋を作ってくださいという指示の方がよりすぐに行動できます。
この鍋の例と同様に勉強も具体的に何をするかを決めたほうがすぐに行動できます。「勉強をしよう」よりも「単語を覚えよう」、「単語を覚えよう」よりも「不規則変化の動詞を覚えよう」という目的にしたほうがすぐに勉強に取り掛かれるようになります。