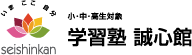こんにちは。講師の中村(元)です。
さて、早速ですが質問です。
「『yはxの関数である』の定義を述べよ」
「絶対値の定義を述べよ」
「有理数の定義を述べよ」
これらの質問にどれくらい正確に答えることができるでしょうか。
実はこれらの質問の答えは教科書の該当単元の1番最初に書いてあります。特に前2つは中学1年生の教科書のかなり前の方に書いてあるほど基本的な定義です。
残念ながらこの質問に正確に答えられる学生は少ないです。しかし、答えられなくても数学が得意であったり、好きであったりする学生が多いことも事実です。では、この定義を正確に覚える必要性とはなんなのでしょうか。
サッカーに例えてみましょう。
友達と公園でサッカーをする子ども全員がサッカーのルールを完璧に把握しているでしょうか。答えは否です。場合によっては「手を使ってはいけない」「ボールを相手のゴールに入れる」の2つだけをルールとしている場合もあるでしょう。
「楽しむ」という点にだけ重点をおいて考えれば、これでもなんの問題もないのです。しかし、プロのリーグにあるような高度に戦術的でハイレベルなサッカーを楽しむためにはルールを完璧に把握していることが必要不可欠となってきます。
「定義」の考え方はこの例によく似ています。
厳密な「定義」を知らなくても漠然としたルールと教科書に載っている解法から答えを導き出すことができますし、その上である程度の成績を修めることは可能です。
しかし、それはおもしろくありません。「なぜその解法を使うことで答えを導き出せるのか」と考えたとき、「定義」を知らなければその理由にたどり着くことは不可能です。人間に知的好奇心がある以上、勉強のおもしろさとは物事の本質を探ることだと私は考えています。だとすれば、単に解法をたどった勉強がおもしろいとは考えにくいです。
また、理系高校生には記述解答式の数学が必要不可欠となりますが、この「定義」をあまり意識していないと全く解答として成り立たないことがよくあります。例えば「aは偶数だからa=2nと表せる」と書いてある場合が多いのですが、これは完全に誤答です。なぜならば「n」が定義されていないからです。「aは偶数だからa=2n (nは整数) と表せる」といった書き方を自然とできるような感覚を身につけることは非常に大事です。
大学に入ると「定義」の考え方はさらに複雑になります。複数の「定義」すべき文字や概念が登場するため、「どの順番で定義すべきなのか」「aという実数はなんでもいいのか、それとも固定されているのか」などを、誰が見ても、そのようにしか解釈できないような記述をする能力が必要となります。
将来こういった状況に直面した時に混乱しないように、中学生、高校生の頃から「定義」を重視した学習をしてほしいと考えています。
最後に最初の3つの質問の答えを書いて終わりたいと思います。
「xの値を決めると、yの値がただ1つに定まること」 (誤答:「xの値を決めると、yの値が定まること」)
「数直線上における原点からの距離」 (誤答:「数字や文字からマイナスをとった数」)
「(整数)/(整数(ただし0以外))と表すことができる実数」