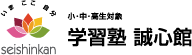塾長の私が目指す学習塾は「自立学習」ができる子供たちを育てること。
それが未来の大人たちへの最高のプレゼントであるといっても過言ではないと信じております。
なので、塾のスタイルとしては関東地方を中心に増えつつある自立学習型が生徒たちの学ぶ力を育み成長を促すにも最適ではないかと考えております。
しかしながら、かなり勉強が遅れていたり、積極的に講師へ質問ができない、自己管理する習慣ができていない、勉強のやり方がわからない中学生が多いうえに部活や宿題、さらには定期テストに追われているのが生徒たちの現状。
そんな彼らを指導するにあたり試行錯誤しながら辿り着いたのが誠心館のレギュラーコース(90分個別指導+90分の自立学習)です。
1対3~4で90分の個別指導を受ける。さらに残りの90分は自分のペースで勉強するという仕組みで生徒たちの自立と自律の精神を養う。
その基礎を築いた上で学習効果を上げていく。高校生になっても困らない(塾に行かなくてもいい?)自分だけの勉強方法を掴む(んでほしい。。。)
毎日、講師と生徒が本気で対峙しながら一歩づつ前進する姿を見ながら想うことは表面上は勉強を教えているけれど、生徒たちの気持ちを考えながら「やる気」を引き出す根気のいる作業であるということ。
これは大げさに言うと「魂の教育」という言葉が当てはまるのではないでしょうか?
人生は死ぬまで勉強だし未来は「いま、ここ」の積み重ね。生徒たちには「いま、ここ」を大事にしてほしいと思います。
写真は須貝先生、丸野先生、伊東先生が生徒たちを指導しているところ。
1問1問が真剣勝負です。