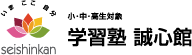こんにちは、中村(宏)です。
今回の話はドラマの話です。リーガル・ハイを知っていますか?半沢直樹で大人気の堺雅人の出世作です。
大まかなストーリーは堺雅人演じる悪徳(?)弁護士の古御門研介があの手この手で圧倒的不利な裁判を逆転するといったものです。私個人的には堺雅人の演技もとても大好きです。
主人公の古御門は裁判を有利に進めるために、証拠を偽装したりを作ったり相手サイドの人間に嘘の情報を流したりと勝つためにはどんな手段でも使う弁護士です。生徒にはそういう人間にはなってほしくないと思いますが、古御門を見習うべき点もあります。
それは「調べる」ことです。古御門は裁判では卑怯な手を使いますが、勝つために事件の詳細などを調べることは徹底的にやっています。このドラマを見た人にしかわからない話ですが、古御門が絹美村編で裁判で徹底的に戦うべく村の老人たちを勇気づけるシーンでは、どれだけ古御門が村のことを調べてるかがわかります。
現代の学校教育では、この「調べる力」は身に着けることが難しいです。物事を調べるには、まず何かに疑問を持つ必要があります。例えば、中学英語ではsomeとanyは、肯定文ではsome、否定文ではanyを使うと習います。はっきり言って、これは嘘で、anyは肯定文でも使えるし、someは否定文でも使えます。では、本当はどのような違いがあるのでしょうか。今回のブログではあえてその答えは書かないので、気になる人は調べてみましょう。(それでもわからない人は質問してください(笑))
調べることは、文章で勉強する練習にもなります。学校教育では先生が口頭で勉強を教えてくれますが、学校を出た後は自分で文章を読んで勉強することが大事になります。
自分で「調べる」勉強は社会に出てからでもとても役に立ちます。