
こんにちは。中村(宏)です。
私の好きな漫画のひとつに頭文字Dがあります。この漫画は自動車レースを題材にした漫画です。この漫画からスランプを乗り越えるヒントを学んだので今日はそれを紹介します。(※一部ネタバレを含みます)
この漫画には、2人の主人公ドライバーが登場し、それぞれのドライバーが最終レースの前にそれぞれの課題をクリアします。ドライバーの一人は高橋啓介という名前であり、彼の性格は熱血漢であり真面目です。彼はその性格から毎日一生懸命練習に取り組みますが、ある日実力が伸びなくなってしまいます。そこで彼の兄であり監督である人物が彼にある課題を出します。
その課題の内容は、
①コースの中の区間ごとに目標タイムを設定する
②目標タイムは自己ベストタイムより遅いタイムを設定する
③目標タイムと同じタイムで走る(遅いのはもちろん、速いのもダメ)
④もしも目標通りのタイムで走れなかった区間があった場合はその理由を考える
というものです。
雨が降ったり体調がわるかったりする日も同じ目標タイムで走るというルールもありました。
それまで最高タイムだけを求めてひたすら全力を出して練習していた主人公は、この練習で車をコントロールする技術を身につけ、全力の走りにも更なる磨きがかかります。
この漫画の中で「(走りを)コントロールすることは全力を出すことよりも難しい」と主張されています。
「コントロールをすることは全力を出すことよりも難しい」という言葉は様々なことに当てはまる言葉だと、私は考えています。スポーツなどでも、一生懸命に練習することはとても大事なことですが、何をすべきかを考えたり自分自身の課題をクールに考えることもとても大事です。
この言葉はもちろん勉強にも当てはまります。誠心館で勉強する場合、一番最初の課題になるのが3時間しっかり勉強することです。自分で考えて勉強することは、はじめはとても難しいことです。もちろん3時間の勉強も1、2か月も続ければ慣れることができます。大事なことは、それからどのように勉強するかです。塾での1日の目標を「3時間勉強する」という目標から「3時間の間に4種類の勉強を終わらせる」という目的に変化させることで、勉強の目的をさらに効率化することが出来ます。勉強の目標は時間ではなく、量で設定することがおすすめです。量で目標を設定することで、体調の少し悪い日でもこれだけ終わらせなければならないというモチベーションができて、しっかり勉強することが出来ます。また、勉強量から試験勉強にかかる時間を逆算することもできます。
「勉強し続ける」一生懸命の勉強に慣れたら、「やるべき勉強を短時間で終わらせる」コントロールする勉強に挑戦してみてください。
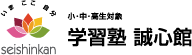
 こんばんは!講師の丸野です。
こんばんは!講師の丸野です。 こんにちは。講師の中村元幾です。
こんにちは。講師の中村元幾です。 こんにちは、上熊須です。
こんにちは、上熊須です。 こんばんは。講師の宮本です。大学の授業も本格的に始動し、実験に部活動に忙しく動いております。忙殺の日々でも学習したことはきちんと復習しなければ自分の中に定着しません。そこで大切なのが、授業内容を文字あるいは図で記録したノートです。
こんばんは。講師の宮本です。大学の授業も本格的に始動し、実験に部活動に忙しく動いております。忙殺の日々でも学習したことはきちんと復習しなければ自分の中に定着しません。そこで大切なのが、授業内容を文字あるいは図で記録したノートです。